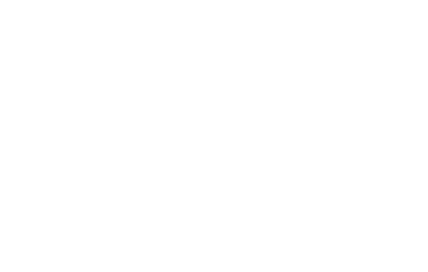

PROFILE
1971年、東京都生まれ。立正大学客員教授。株式会社ハニーコミュニケーションズ所属。
1995年のマカルー(8463m)登頂。1996年には、エベレスト(8848m)とK2(8611m)の連続登頂に成功。アルパインスタイルも積極的に取り入れた速攻登山で8000m峰に挑み続け、2012年に14座目となるダウラギリに登頂に成功。日本人初、世界29人目となる8000m峰14座完全登頂を果たす。
2013年、植村直己冒険賞、文部科学大臣顕彰スポーツ功労者顕彰を受賞。
現在は、未踏峰への挑戦を続ける傍ら、登山経験を生かし、野外教室や防災啓発などの社会貢献活動にも取り組んでいる。
HISTORY
| 1971年 | 誕生 |
|---|---|
| 1986年 | 都立一橋高等学校 山岳部へ入部 |
| 1990年 | 立正大学 山岳部へ入部 |
| 1991年 | シシャパンマ(8027m)東稜下部初登攀北面7500m地点まで |
| 1995年 | マカルー(8463m)遠征隊に参加し8000m峰初登頂を成功 |
| 1996年 | 8000m峰の2座目エベレスト(8848m)、3座目K2(8611m)の登頂成功 |
| 1999年 | リャンカンカンリ(7535m)世界初登頂成功 |
| 2001年 | 国際公募隊に初参加し4座目のナンガパルバット(8126m)登頂成功 |
| 2003年 | カンチェンジュンガ(8586m)北面7500m地点まで |
| シシャパンマ(8027m)南西壁6500m地点まで | |
| 2004年 | 5座目アンナプルナ(8091m)、6座目ガッシャブルムI峰(8080m)登頂成功 |
| 2005年 | 7座目シシャパンマ(8027m)登頂成功 |
| エベレスト(8848m)中央ロンブク氷河側より北稜7700m地点で意識を失い救出される | |
| 2006年 | 8座目カンチェンジュンガ(8586m)登頂成功、14座完登を表明しプロ登山家を宣言 |
| 2007年 | 9座目マナスル(8163m)登頂成功 |
| ガッシャブルムII峰(8035m)通常ルート7000m地点で雪崩に巻き込まれ重傷を負い救出される" | |
| 2008年 | 10座目ガッシャブルムII峰(8034m)、11座目ブロードピーク(8051m)登頂成功 |
| 2009年 | 12座目ローツェ(8516m)登頂成功 |
| 2010年 | チョ・オユー(8201m)7700メートル地点まで |
| 2011年 | 13座目チョー・オユー(8201m)登頂成功 |
| 2012年 | 14座目ダウラギリ(8167m)登頂成功 |
| 日本人初、世界で29人目の(8000m峰完全登頂)14サミッターとなった | |
| 2013年 | 第17回植村直己冒険賞を受賞、4月より立正大学客員教授に就任 |
| 文部科学大臣顕彰 スポーツ功労者顕彰 受賞 | |
| 2014年 | マナスル2回目の登頂 |
| 2016年 | マナスル日本隊初登頂60周年記念事業を主宰 |
| 毎日新聞社・立正大学と共に各種イベントを開催 |
写真:14PROJECT事務局提供
竹内洋岳は、日本人で初めて8000m峰14座全山登頂を果たした人物であるとともに、登山をスポーツと捉え、フェアなスポーツとして3つの要件を提唱し、「プロ登山家」としての活動を行っています。
登山をスポーツにするためには、他のスポーツと同じように、プロがいること、ルールや審判があること、観客がいるということ、この3つを作り上げる必要があります。
とりあえずプロがいるということが必要なので、私がプロ登山家と名乗る。登山にはルールと審判がないということは、自分でルールを決めて審判をすればいいので、私の場合は、あらかじめ14座を登りきってみせるという宣言をすることがルールになります。自分が審判で、死なないで登って下りてくるというのが自分へのジャッジになる。そして通信技術を駆使することで、衛星回線を使って出来るだけリアルタイムに登山の様子を観客に見てもらう。
ダウラギリではGPSを使ってリアルタイムで自分の居場所をインターネット上の地図上に見せていきました。GPSで私の居場所が地図上に表示されることは、頂上に近づいていくのをリアルに見てもらうのと同時に、途中で動かなくなるという可能性もある。私は死んでしまうのを見られていいと思うんです。登山では、確かに死ぬこともあるのですから、隠すものではない気がします。必ずしも登って下りる勝ち試合を見てもらうだけではなくて、負け試合も見られても構わない。それゆえに見てくれていた人たちが観客になっていく。
スポーツは間違いなくアマチュアが発展させていきます。プロの選手がいればいるほどアマチュアが存在できる。
プロやアマチュア、趣味、レジャー、全部があってスポーツになっていくと思います。
以下、「標高8000メートルを生き抜く 登山の哲学」より抜粋
「死ぬ想像ができなければ、死なないことの想像はできません。思いつく限りのあらゆる『死に方』を並べ立て、それを回避するための計画を考えるんです。登山家はいかに多く『死に方』を想像できるかを競っていると言ってもいいかもしれません」
「14座登ったら何が見えるのか。答えは14座以外の山でした。地球上には無数に山がある。私はそのうちの14座に登っただけ。世界には私がまだ登っていない山がいくらでもある。それは全て私の好奇心をかき立ててくれるものです」
「私は14座登頂を達成するのに17年かかりました。その中では1度の挑戦で登頂に至らなかったこともあります。けれど、たとえ引き返したとしても、再びその山に登るならば、それは失敗ではなく、すべて登頂のための過程でしかない。私にとっての『失敗』は『死』。つまり、死なない限りは失敗ではないのです」
「私にとっての経験とは、積み重ねるものではなく、並べるものなのです。経験が増えれば増えるほど、数多くのディテールが知識となって記憶にインプットされます。そのディテールとディテールの隙間を埋めていく作業が“想像”です。だから、経験の積み木のすべてが見渡せるように、テーブルの上に広げておく。そして、並べてある位置を移動させたり、順番を入れ替えたりしながら、隙間を埋め尽くすほど想像を膨らませていく・・・想像できることが多ければ多いほど、登山は面白くなり、危険も回避できる」
LECTURE
RESULTS
日本人初・世界で29人目の8000m峰完全登頂に成功、14サミッターとなった
14座のうち、11座は無酸素登頂を果たす
『文部科学大臣顕彰、スポーツ功労者顕彰』
第17回「植村直己冒険賞」
第15回「秩父宮記念山岳賞」を受賞





![NHK出版新書 407「標高8000メートルを生き抜く 登山の哲学 」[著] 竹内洋岳](https://honeycom.co.jp/hirotaka-takeuchi/wp-content/themes/honeycom-takeuchi/assets/images/img-climbing-philosophy01.jpg)

